「Webデザイナーってもう稼げないんでしょ?」「将来性ないって聞いたけど……」
最近、SNSやブログ、YouTubeなどでも、“Webデザイナーはオワコン”という言葉を目にする機会が確実に増えてきました。
実際、「Webデザイナー なくなる」と検索している人も多く、不安を抱えている方は少なくないはずです。
-
これからWebデザインを学ぼうとしている人
-
スキルを活かして転職したいと考えている人
-
すでに現場で仕事をしている人
それぞれの立場で「このままWebデザイナーとしてやっていけるのか?」という不安は、決して他人事ではないでしょう。
私は現在、Web制作歴15年以上の現役デザイナー兼ディレクターとして活動しています。
この業界のリアルを見続けてきた立場から、
「Webデザイナーは本当になくなるのか?」「今後どうやって生き残っていけばいいのか?」
その答えを、実体験を交えながらお伝えしていきます。
結論:「なくなるWebデザイナー」はいる。でも全員じゃない。
よく聞かれる質問があります。
「Webデザイナーって、将来的に本当にいらなくなるんですか?」
これに対して私の答えは、**「仕事がなくなる人はいる。でも、必要とされ続ける人もいる」**です。
つまり、“職業としてのWebデザイナー”が完全に消えるわけではありません。
たとえば、今でもチラシやポスターを作るグラフィックデザイナーが存在していますよね?
それと同じで、Webデザイナーも役割を変えながら残っていくはずです。
ただし──
「デザインだけをやる人」「狭い範囲の作業だけしかできない人」は、確実に減っていくでしょう。
今はCANVAのような無料ツールでも、ある程度見栄えのするバナーやLPが誰でも作れる時代です。
こうなると、「本当に大切なところだけプロに任せる」「テンプレで十分なものは自分でやる」という流れが加速していきます。
結果として、単なる“作業者”としてのWebデザイナーは、真っ先に淘汰される可能性がある。
(…ちょっと怖い話ですが)
一方で、**思考力・提案力・技術対応力を備えた“価値を生み出せるデザイナー”**は、これからの時代にますます求められる存在になるでしょう。
すでに、**「言われたものを作る人」と「ビジネスを動かす人」**の二極化が進み始めている──そう感じています。
なぜ「Webデザイナーはなくなる」と言われるのか?
1. ノーコードツールの進化
STUDIOやWix、ペライチといったノーコードツールの普及により、「コードが書けなくても、Webサイトが作れる」時代が本格的に到来しています。
さらに最近では、Adobeのデザインソフトすら使わずに、テンプレートとテキスト入力だけでそれっぽいサイトが完成するケースも増えてきました。
加えて、ChatGPTや画像生成AIなどの登場で、文章作成やデザインの一部も自動化が可能に。
こうした流れにより、個人事業主や小規模ビジネスでは「もうデザイナーを雇わなくても、ある程度のサイトは作れる」と考える人が増えているのも事実です。
とはいえ、現時点ではまだ“それっぽく見える”程度。
個人的には「テンプレ感が強く、かゆいところに手が届かない」仕上がりが多い印象です。
自由度が低く、世界観やブランディングにこだわりたい場合には、どうしても物足りなさを感じます。
とはいえ、この進化スピードは恐ろしいほど速く、「あと数年でかなりの精度に達するのでは…?」と不安を感じている人も多いでしょう。
つまり──
「テンプレを超えられないWebデザイナー」にとって、ノーコードやAIは確実に脅威となっているのです。
2. 単価の下落と「安くて速い」市場の拡大
最近では、ココナラやクラウドワークスなどのクラウドソーシングで、1万円以下や3万円以下でLP制作といった案件も珍しくありません。
正直、会社で案件を請けていると「その金額はないでしょ」と思うレベルです。
だって、そんな価格でどれだけの時間をかけて作業するつもりなのか? コンビニのバイトのほうがまだ時給が高いんじゃないか──と、正直感じてしまいます。
こういった案件の背景には、「とにかく安く・早く欲しい」というニーズが一定数あることが挙げられます。
例えば「実績を作りたい」「駆け出しでもお金が欲しい」という理由で、極端な低単価でも受けてしまう人もいます。
でも現実には、そういった案件に限ってクライアントの質が悪いことも多く、細かい修正依頼やクレームが多い傾向があります。
私自身、そういう案件は基本的にスルーしています。割に合わない上に、メンタルを削られることも多いですからね。
加えて、ここに参入しているのは「職業訓練校を出たばかりの人」や「ネットで独学してフリーランスを名乗っている人」など、まだプロとしての経験が浅い層が多く、競争が過剰になっている市場でもあります。
当然ながら、この領域は“早い者勝ち”かつ“安い者勝ち”の世界。
ここに依存してしまうと、単価も時間もどんどん削られ、結局は消耗して終わるだけです。
「稼げるWebデザイナー」を目指すのであれば、こういった市場はむしろ避けるべきフィールドだと私は考えています。
3. 作業を“こなすだけ”では、いずれ仕事がなくなる
Webデザインというと「見た目を整える仕事」と思われがちですが、本質は“問題解決”です。
しかし現場では、そうした本質を忘れ、「ただ整えて出すだけ」のデザイナーも少なくありません。
たとえば──
写真を左、文章を右に置いただけ。
なんとなく余白を空けて、なんとなく色を塗って、完成。
これって、基本レイアウトを知っていれば誰にでもできますよね?
でも、なぜその構成にしたのか?
なぜその色なのか?
どんな意図でそのフォントを使ったのか?
それを言語化できないデザイナーは、いずれAIやテンプレートに置き換えられてしまいます。
いまはまだ「整っているだけ」で喜ばれることもあるかもしれません。
でもこれからは、「なぜ?」に答えられることが当たり前になります。
つまり、自分の頭で考えず、ただの“手”として作業するだけのデザイナーは、確実に「なくなる側」に入ってしまうということです。
でも、私は今も現役で仕事をしている
ここまで読んで、「Webデザイナーって、もう危ないんじゃないの?」と不安に感じた方もいるかもしれません。
確かに、昔と比べて**“楽に稼げる仕事”ではなくなった**と思います。
「Webデザインって楽しそう」という軽い気持ちでこの世界に飛び込む人も多いですが、
実際は思ったより稼げなかったり、継続的に仕事が取れなかったりで、残れる人は決して多くありません。
ですが、私は今もWebデザインの仕事でご飯を食べていますし、今の方がむしろやりがいを感じています。
理由はシンプルです。
「ちゃんと考えて、ある程度のクオリティで作れる人」が、まだまだ重宝される世界だからです。
いまのWeb業界では、「作れる人」自体はたくさんいます。
でも、「なぜそうするのか?」「どうすれば成果につながるのか?」といった本質を理解して提案できる人は、圧倒的に少ないんです。
企業側も、ただ安くて早い制作を求めているわけではありません。
実績はどうか? 信頼できる人か? 意図を理解してくれるか? というところまで見ています。
私自身、華やかなキャリアだったわけではありません。
職業訓練校で学び、派遣・アルバイトから経験を積み、社員として働きながら少しずつコーディングやディレクションを覚えてきただけです。
決して器用なタイプでも、天才肌でもありません。
でも、変化に適応し、常に「どうすればもっと良くなるか?」を考える癖を持ち続けてきたことで、
今もこうして仕事を継続できているのだと思います。
Webデザイナーが「なくならない」理由
1. ビジネス理解と提案力のある人は求められる
クライアントは「なんとなくオシャレなサイト」を欲しがっているわけではありません。
成果につながる設計・導線・言葉選び・ターゲット設定──そこまで考えて提案できる人は、代替がききません。
AIは「指示されたこと」はできますが、「そもそも何が問題なのか」は読み取れません。
ここに人間の価値があります。
2. ブランディングや体験設計は人間の領域
Webサイトは「情報を届けるだけの場」ではなくなっています。
世界観や雰囲気、ブランドの価値観を伝えることが、より重要になっています。
これは単なるパーツ配置やレイアウトではなく、見る人の感情に訴える総合的な体験づくりです。
AIにはまだ難しい領域です。
3. 実装・デザイン・ディレクションの「掛け算」が強い
私は今、デザイン・コーディング・ディレクションを全て行っています。
小規模プロジェクトであれば、一人でまわせる人材は重宝されます。
逆に、どれか一つだけしかできないと、選ばれる機会は減ってしまいます。
これからWebデザイナーとして生き残るには?
じゃあ、どうすれば「なくなる側」ではなく「求められる側」に入れるのか。
ここは重要な部分なので、実体験ベースで書きます。
1. 「作業者」から「戦略者」へ
言われたものを作るだけの人は、今後AIにも負けます。
クライアントが気づいていない課題を見つけて、「こうしたらもっと良くなりますよ」と提案できる力が求められます。
2. ツールを恐れず、味方にする
私はChatGPT、Midjourney、STUDIO、Figma AIなどを日常的に使っています。
これらを「使いこなす」ことで、制作時間が短縮され、空いた時間を“考える”ことに使えるようになります。
道具は怖がらず、味方にしましょう。
3. SNSやブログで「見つけてもらう人」になる
ただスキルを磨くだけでは、仕事にはつながりません。
私はこのブログやSNSを通じて直接依頼を受けることもあります。
「誰に頼むか」が大事な時代、発信力はスキルと同じくらい重要な武器です。
まとめ:Webデザイナーは“なくなる”のではなく“進化”する
Webデザイナーという仕事は、確かに「昔のままの形では」生き残れないかもしれません。
でもそれは「なくなる」こととは違います。
むしろ、進化し続けることで、より自由に、より創造的に働ける仕事へと変わってきているとも言えます。
「なくなる」と言われて不安になるのは、何もおかしくありません。
でも、そこで立ち止まらずに「どうすれば求められるか?」を考える人に、道は開けていくはずです。
15年目の私がいまも仕事を続けているのが、その証拠です。
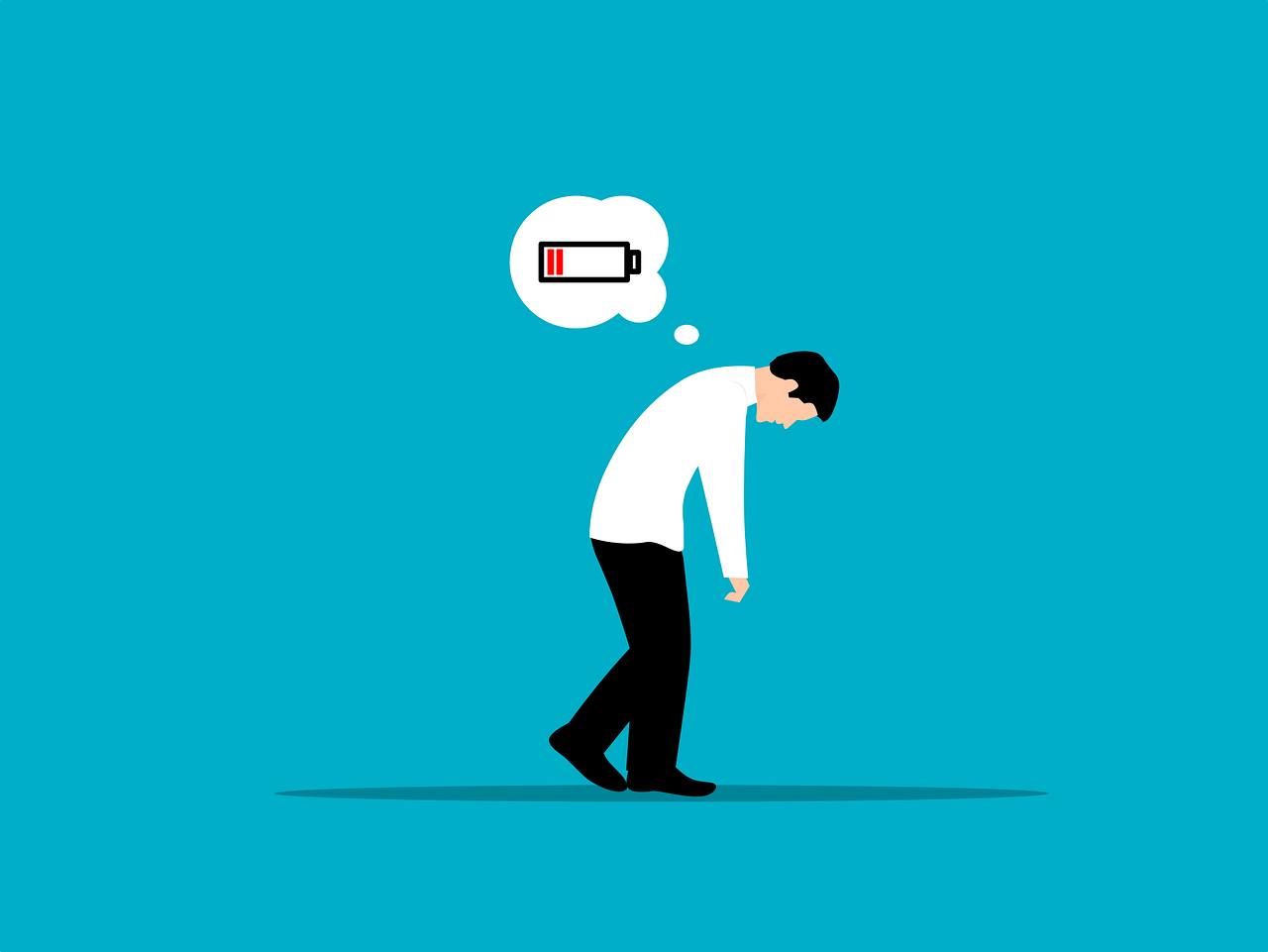


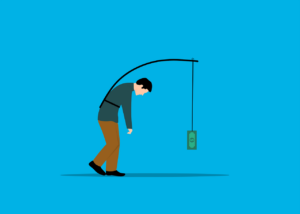






コメント